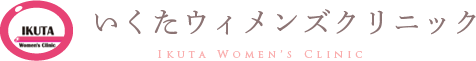妊の大きな原因のひとつともいわれる、卵管通過障害。
卵管に障害があると、精子と卵子が出会えずに受精ができず、不妊となってしまいます。
卵管通過障害はいくつか原因があり、原因を探って、適切な治療をしていく必要があります。
どんな原因が考えられ、検査方法や治療方法はどのような方法があるのでしょうか。
卵管通過障害について、まとめました。
卵管通過障害とは

受精卵の通り道となる卵管は、子宮の左右にあり、だいたい10cm程度の長さがあります。
卵管通過障害とは、卵管がなんらかの理由で詰まってしまったり、狭くなってしまう状態です。
- ・卵管通過障害とは
- ・卵管通過障害の自覚症状は
卵管通過障害とは、さらに自覚症状にはどのような症状があるのかを、確認しておきましょう。
卵管通過障害とは
卵管通過障害とは、卵管の閉塞や狭窄により、卵子が通過できなくなっている状態です。
不妊症に悩む女性の30%が卵管通過障害だといわれており、珍しい疾患ではありません。
卵管が閉塞していると、受精卵が通過できないだけでなく、そもそも受精が困難となります。
卵管の狭窄がおきていると、受精卵がうまく着床できずに子宮外妊娠となってしまう可能性もあります。
卵管は10cmほどの長さだとお伝えしましたが、1番細い部分の直径は約1mmという細さです。
閉塞や狭窄があれば、適切な治療をしていく必要があります。
卵管通過障害の自覚症状は
卵管通過障害は、基本的には無症状で痛みなどがありません。
そのため不妊治療をして、初めて疾患に気付くという方も少なくありません。
稀にある自覚症状としては、おりものの増加や下腹部の重たい感じなどがあります。
しかしおりものの変化や下腹部の違和感だけで、卵管通過障害だと確定はできません。
卵管通過障害の原因

卵管通過障害になってしまう理由として、このような原因が考えられます。
- ・クラミジア感染症
- ・子宮内膜症
- ・卵管周囲の癒着
卵管通過障害の原因について、ご紹介します。
クラミジア感染症
クラミジア感染症は、日本で最も多い性感染症のひとつです。
性交渉などが原因でクラミジア・トラコマチスという病原菌が感染します。
女性は8割の方が無症状で、自覚症状がありません。
しかしクラミジア感染症が悪化すると、子宮頚管、子宮、卵管や卵巣にも影響がでる場合があり、不妊の原因にもなります。
クラミジア感染症によって、卵管が周囲と癒着して卵管障害が起こる原因となります。
子宮頚管部に感染して炎症が起きると、クラミジア性子宮頚管炎という形で影響が出るケースもあります。
子宮内膜症
子宮内膜症は、膀胱や卵巣など、子宮以外の場所で内膜のような組織が増えてしまう症状です。
子宮内膜またはそれに似た組織が何らかの原因で、本来あるべき子宮の内側以外の場所で発生し発育する疾患が子宮内膜症です。
日本産科婦人科学会より引用
20~30代の女性で発症することが多く、そのピークは30~34歳にあるといわれています。
子宮内膜症になると、腹痛や月経痛、排便通性交痛を感じる方が多く、痛みは代表的な症状といえます。
さらに卵管障害の原因になりますので、妊娠を望む方にとっては不妊の原因となります。
子宮内膜症の原因としては、これらの原因が考えられます。
- ・初潮の低年齢化
- ・女性1人あたりの出産回数の減少
- ・生理周期の乱れ
- ・欧米化した栄養過多の食生活
しかしどれも直接的な原因と断定できるものではなく、具体的な理由はわかっていません。
卵管周囲の癒着
卵管が癒着して閉鎖や狭窄し、卵管通過障害となってしまう場合もあります。
- ・クラミジアの炎症による癒着
- ・開腹手術による癒着
クラミジアの炎症による癒着だけでなく、過去に開腹手術の既往歴がある方は、卵管周囲の癒着が起きているかもしれません。
子宮外妊娠や帝王切開などが理由の手術を受けた経験のある方は、医師に相談してみるといいでしょう。
卵管通過障害の検査

卵管通過障害があったとしても、痛みや自覚症状のない状態です。
そのため診断には、クリニックでの検査が必要となります。
卵管の通りやすさへの評価、閉塞や狭窄の有無を調べるには、いくつかの方法があります。
卵管通過障害と診断されるまでに行われる検査には、以下のような検査があります。
- ・クラミジア抗体検査
- ・X線子宮卵管造影検査(レントゲン)
- ・超音波下子宮卵管造影検査(エコー)
- ・通水検査
卵管通過障害の検査について、ご説明します。
クラミジア抗体検査
卵管通過障害の原因となる、クラミジア感染症をチェックする検査です。
不妊の原因を調べる際の検査として、クラミジア抗体検査は早い段階で実施されます。
クラミジア抗体が陽性だとわかると、次のステップとして子宮卵管造影検査や癒着の確認へ進みます。
卵管因子による不妊の場合、クラミジアが原因となるのは6割~7割程度です。
クラミジア抗体検査の方法は、採血です。
抗原検査だと、尿検査や膣分泌物、肛門分泌物で検査を行います。
X線子宮卵管造影検査(レントゲン)
X線子宮卵管造影検査とは、不妊治療においては多くの場合において必要になる検査です。
子宮と卵管の通り具合を検査するための造影剤を使った特別なレントゲン撮影である。 子宮口からカテーテルを入れ、子宮頸管を通って子宮まで差し込み、バルーンを膨らませて固定する。
Wikipedia子宮卵管造影検査より引用
その後、造影剤を流し込み、レントゲンを撮影する。
卵管の通過性を確認するための検査です。
子宮内にチューブを固定する際には激痛が走るともいわれますので、不安になる方も多いでしょう。
高粘度の造影剤を細い卵管に注入しますので、注入の際にも痛みが発生します。
しかし子宮卵管造影検査で造影剤を注入した後は、卵管の通りがよくなり妊娠しやすくなるともいわれています。
検査後をゴールデンタイムと呼ぶドクターもいます。
X線子宮卵管造影検査の注意点
X線子宮卵管造影検査は、以下のような条件に当てはまる方は受けられない場合もあります。
- ・ヨード造影剤アレルギーの方
- ・甲状腺疾患をお持ちの方
- ・糖尿病のお薬メトホルミンを服用中の方
- ・妊娠の可能性がある方
- ・クラミジア抗体検査を受けていない方
X線子宮卵管造影検査は、造影剤を使用したレントゲンの検査です。
大量の放射線は受精卵を死亡させてしまう恐れがありますので、妊娠の可能性のある方は検査ができません。
子宮卵管造影検査を予定している方は、月経後から避妊しておくようにしましょう。
超音波下子宮卵管造影検査(エコー)

先ほどご紹介した子宮卵管造影検査は、レントゲンでの検査です。
超音波下子宮卵管造影検査とは、レントゲンではなくエコーで卵管の通過を調べる方法です。
カテーテルを挿入し、バルーンを固定するのは同じですが、造影剤ではなく生理食塩水及び空気の混合液(以前の物は液の精度に問題があり現在は出回ってはいませんし、バイエルの物はディスポでかなり高価で患者さんからもお金をもらえないので行う施設はありません)を注入します。
注入した混合液の流れをエコーで確認し、卵管の通りを確認していきます。
レントゲンではなく、エコーで検査をすると以下のようなメリットがあります。
- ・放射線被爆の心配がない
- ・X線子宮卵管造影検査と同等の高性能
- ・ヨード造影剤アレルギーの方も検査可能
- ・甲状腺疾患をお持ちの方も検査可能
- ・X線子宮卵管造影検査より痛みが少ない
どちらの子宮卵管造影検査が適しているかは、医師と相談して決めていきましょう。
通水検査
通水検査とは、生理食塩水を子宮内に注入し、卵管の通りを確認する検査です。
子宮卵管造影検査と比較すると、診断情報や診断性の高さは劣ります。
痛みの少ない検査ではありますが、卵管に閉塞や狭窄があると痛みを感じる場合もあります。
卵管通過障害の治療法

卵管通過障害だと診断されたら、症状に合わせた治療を開始します。
治療法は主に3つあり、卵管通過障害の原因や症状に合わせて適切な方法を選んでいきます。
- ・薬物療法
- ・手術
- ・体外受精
それぞれの方法について、ご説明します。
薬物療法
クラミジア感染症や子宮内膜症が原因の卵管通過障害が認められた場合には、薬物療法から治療をスタートします。
クラミジア感染症の治療には、抗生物質が処方されます。
性感染症はパートナーが感染していないとしても、2人で治療をするのが基本です。
1週間程度の薬の服用が目安となり、陰性を確認すれば完治となります。
子宮内膜症の場合には、ホルモン剤やピルが処方されます。
ホルモン剤を用いた治療では、閉経したような状態となり、排卵や生理を意図的に止める治療法です。
妊娠を望む方であれば、どのような方法が適切なのかを医師と話し合う必要があるでしょう。
手術
検査によって卵管の閉塞や狭窄が見つかった場合には、卵管鏡下卵管形成術を行います。
子宮にカテーテルを通して卵管の入り口を確認し、卵管にバルーンを挿入していきます。
バルーンによって、卵管の閉塞部分や狭窄部分を広げていく手術です。
卵管鏡下卵管形成術での治療をした方は、多くの方が3ヶ月以内に妊娠されています。
卵管の末端部分の病気が見つかった方は、腹腔鏡手術での治療となります。
卵管通過障害の原因に対して、適切な治療を行うのが重要です。
体外受精
卵管通過障害と診断された方で、妊娠を急ぐ場合には体外受精という選択をされる方もいます。
癒着が進んでいる、卵管障害が重度であると診断される場合には、卵管を使用せずに妊娠できる方法もあると覚えておくといいでしょう。
ただし卵管に水が溜まる「卵管水腫」がある場合には、着床率が低下してしまいますので、卵管切除術が必要になる場合もあります。
体外受精は卵管通過障害の治療というよりは、不妊治療の対応のひとつとなります。
卵管通過障害で自然妊娠
卵管通過障害が不妊の原因だと診断された方は、自然妊娠の確率は低くなると考えておきましょう。
しかし卵管は左右2本ありますので、片側のみの卵管通過障害であれば自然妊娠の可能性もあります。
卵管通過障害は、片方の卵管に異常があるケースと、双方の卵管に異常があるケースがあります。
一般的に卵管通過障害は不妊の大きな原因だと考えられますので、片方であっても卵管通過障害が認められた場合は、治療に踏み切った方がよいでしょう。
女性の不妊の原因

不妊の原因は男性側にも女性側にもある可能性があります。
女性の不妊の原因として考えられるのは、卵管通過障害だけではありません。
- ・卵管因子
- ・排卵因子
- ・子宮因子
- ・頸管因子
女性の不妊の原因について、まとめました。
卵管因子
卵管因子とは、卵管通過障害も含めた、卵管の異常に関する要因です。
卵管因子は不妊の原因の中でも、割合の多い症状のひとつです。
2003年に日本受精着床学会が行なった不妊治療患者によるアンケート調査では、男性因子33%、卵巣因子21%、卵管因子20%、子宮因子18%、免疫因子5%、その他4%であった。
日本産婦人科医会より引用
卵管因子には、ピックアップ障害という症状もあります。
卵管の先にある卵管采が、卵子をうまくピックアップできずに卵管に取り込めなくなってしまう状態です。
このように、卵管因子と一口にいっても、不妊にはさまざまな要因が考えられます。
排卵因子
排卵がうまく起きていない、成熟していないというより適当な時期に排卵刺激が起こらず過熟になった卵子が排卵されてしまう、排卵の異常です。
ホルモンバランスの乱れが原因ですが、排卵がないと妊娠できません。
病院においでにならないのなら基礎体温をつけてみると、無排卵や排卵がたまにしか起きていないという状態がわかるでしょう。
しかし非常に不正確なものですので過信はしないようにしてください。
しかし月経があったとしても排卵されていない「無排卵症」という症状の場合には、自覚症状はありません。
子宮因子
子宮内膜症が卵管通過障害の原因になると先述しました。
子宮内膜症だけでなく、子宮にしこりができる「子宮筋腫」や子宮の形に奇形がある「子宮奇形」も不妊の原因となりえます。(確定的な証拠はないので断定は全くできません)
頸管因子
頸管粘液の分泌量が少量であったり頸管粘液がさらさらにならないために精子の子宮腔への到達数が制限されてしまう「頸管粘液不全」なども不妊の原因となります。
子宮頚管の炎症や、過去の手術が影響している可能性があります。
焦らない妊活を
妊活は精神的な負担もかかります。
「妊活うつ」という言葉もあるほどで、心身のバランスが崩れていくとストレスが増大し、どんどん追い詰められてしまうかもしれません。
卵管通過障害は珍しい症状というほどではありません。
的確に原因がわかれば、確実に治療ができる症状だといえます。
卵管通過障害が完治すれば必ず妊娠できるということではありませんが、治療後に妊娠された方は多くいらっしゃいます。
ご自身とパートナーと、さらには信頼できるドクターと一緒に、焦らずに1歩1歩進んでいきましょう。
最後に大事な事があります。
妊娠するかどうかの一番大きな因子は女性の年齢なのです。
迷っているうちに半年、1年過ぎれば同じ治療を行ったとしても妊娠できる確率は低下してしまいます。とにかくまずは信頼の置ける施設を受診して相談してみることです。